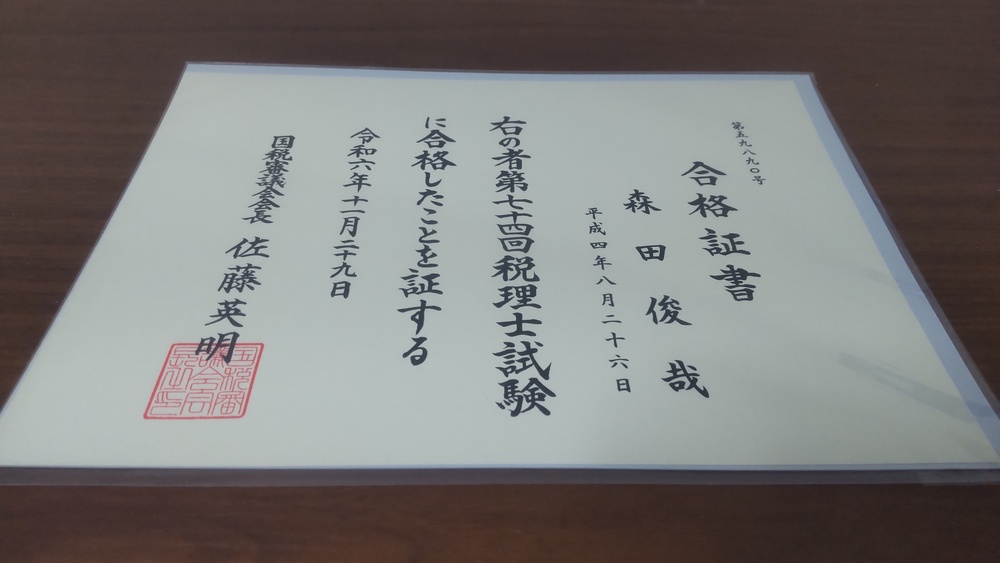初めての税務調査
先日、初めて税務調査に立ち会った。
当然守秘義務があるため詳しく書くことはできないが、かなり大規模な調査になり、肯定的に捉えれば良い経験にはなった。
私も決して顧問業務に手を抜いていたつもりはないが、もっとできること・しなければならないことがあったと反省を得られた。税理士資格所有者でもここまで大掛かりな税務調査に立ち会ったことのない方は少なくないと思うし、税理士事務所の職員の方にとっても日常の業務で参考になる部分があると思う。秘密保持の観点から一部事実と異なる記載も交えながらにはなるが、記録を綴っていく。
今回税務調査が入ったのはかねてから私の所属する事務所で顧問している工業系の法人である。
3年前にも調査が入っており、その際には売上代金が社長個人の口座に入金されていたものが法人の収入になると指摘されたらしい。と言っても社長に着服する意思があったのではなく、元々個人事業だったのを法人化したことに起因する弊害らしい。当時私はまだ事務所にはいなかったので詳細は分からないが、税務署が社長の口座の開示を受けて全ての相手先に連絡するような、税務署側の視点で言えば大事件に発展したようだ。社長に悪意があったかどうかに関わりなく悪質なものとして処理されたのも仕方ないだろう。
そんな経緯があったため、今回は税務署も厳しい手入れをするつもりのようで、職員が2人来て3日間に及ぶという、法人成りして間もない従業員10人程度の会社にしては異例と言える体制で行われた。こちらも税理士4人で応対し、プレハブの事務所はかなりの人口密度になった。
税務調査で聞かれることなどはネットで検索すればいくらでも出てくるが、まさにそのとおりで、会社の概況を説明することから始まった。その中でも「〇〇はやってますか?」「〇〇の利益率はどのくらいですか?」など探りを入れてきているのがよく分かった。
帳簿などの書類は事前に会社にまとめて用意しておいてもらい、元帳や仕訳日記帳をデータでほしいという税務署の要請に応えてcsvやPDFのデータも提供したため、調査は滞りなく進行した。今の時代、資料をデータで貰うことなど当然であるが、こちら側としては少しの記載ミスも許されないようでなんともやりづらい思いだった。
雲行きが怪しくなったのは税務署職員が業務日報を確認し始めてからだった。日報に書かれた案件と売上の請求を全て照合しはじめ、請求が立っていない案件があることを指摘してきた。小さな案件は半ばボランティア的に請け負っていたり、日報は従業員が手書きしているものなので請求と名前が一致しなかったりと、色々事情はあるのだが、税務署はそれでは納得してくれず、全件の請求状態を確認させられた。
また、下請けを行っている100%子会社があり子会社から500万円の請求を出していたのだが、これもまた日報などから原価を算出してきて子会社側に利益が出ていないことを指摘された。そして子会社の調査も行われることとなった。調査と言っても子会社は更に小規模なこともあり30分程度の聴取で終わったが、まさかそちらにまで手が伸びるとは思ってもいなかった。
だが、親会社に戻ってから、元帳上での親会社側での経費計上と子会社側での売上計上の日付が違うことについて質問された。どちらも入力したのは私であり、事務所での処理について問い質してきたのである。端的に言えば子会社は3ヵ月に1回まとめて資料を貰っていることによる差異であり、月のずれはあれど事業年度のずれは起こっていない。それを説明しても仕訳を入力した日付を知りたいと言われ、会計システムのサポートセンターに問い合わせることとなった。今まで入力日の確認はできないと思っていたが実は出力できたため、そこは勉強になった。・・・のだが、まさか事務所側での処理日まで聞かれることになろうとは予想だにしていなかった。
そんなことがありながら流れるように2日が過ぎ、最終日には税務署からの指摘事項が告げられた。全部で5個あり、取引先への聴取も含め調査が今後も継続されるうえに加算される所得金額は1500万円を超える見込みとのことだった。
だが、税務署からの提案として、子会社からの請求500万円を全額寄附金として重加算税も納めることで他の事項は免除として調査も終了するという案を持ち出された。「データの提供など調査に非常によく協力していただいたのでこちらも何とかしたいので」「こんな提案をしたとなっては私が上司に怒られますが・・・」などと理由を挙げてくれた。それらも事実だろうし、あちらも継続調査をしたくないことや重加算税を取れれば溜飲を下げられることなどもあるのだろう。会社としても調査が続くことや取引先に迷惑がかかることを懸念して、結局重加算の提案を呑むこととなった。
・・・と、このように経過を綴るといかにも脱税を働いた悪徳会社のようだが、社長や事務員などは本当に人柄が良く真面目な人物であり、前述のように慈善的な思いから無償で案件を引き受けていたのである。そもそもこの業界は下請になればなるほど立場が弱くなり、売上よりも原価の方が大きくなることも珍しくない。締日後の施工分の未成金計上ができていなかったりと他にも指摘事項はあったのだが、この会社の規模や体制でそこまで管理しきれないというのが正直なところだ。事務所としてもヒアリングベースでは限界があり、かと言って今回税務署がやったように日報や請求を突合して確認するのも非現実的である。
このように決して会社に悪意があったとは言えないのだが、それでもこうして重加算税を取られるまでに至ってしまった。私よりよほど経験豊富な他の税理士達も絶望的な空気に包まれていた。
こうして私の初めての税務調査はボコボコにされて幕を閉じたのだが、日常の業務における元帳の入力を丁寧に行うことの重要性を身に染みて理解した。
記帳代行を行う場合は手入力による部分が大きく煩わしく感じるところであり、自計化している場合も科目や税区分さえ合っていれば良しとしてしまいがちだが、税務署はまず元帳を見て調査を始める。そこで税務署に疑念を抱かせる余地を残してはいけないし、一括償却の特例を適用する場合や逆に該当しない場合など税務上重要なものについては、こちらが取引の内容を確認したという証左としてその旨を付記しておかなければならない。今回の調査でも一括償却適用資産はその旨を付記しておいたし前払費用に計上したものは損金経理分と前払費用計上分に区分した計算根拠を残しておいたのであまり追及されなかったように感じる。逆に前述の子会社側との計上日のずれについては月次締め処理の関係で翌月計上になった旨を記しておけば余計な詮索はされなかったかもしれない。
また、取引先名などを間違えると税務署はデータで見るので妙な欠落が発生してしまう。入力が誤っていたことを証票で証明できたとしても、税務署からは邪推されてしまうだろう。
これまではたとえ税務調査で聞かれたとしても正しい処理をしていれば修正することにはならないので問題ないと思っていたが、余計な部分にまで手を伸ばされかねないし、税務署からの心象が悪くなれば他の部分の調査が深化しかねない。結局、税務調査における入口の部分は固めておかなければならないということである。
今回重加算税を取られたこともあり、3年でも経てば再び調査が入ることは間違いない。その時には正面から殴り返せるようにしておかなければならない。
初めてでこれほど大変な調査になるとは思わなかったしまるで役に立てず申し訳ない思いだが、今後のことを考えれば非常に良い経験となったと言えるだろう。